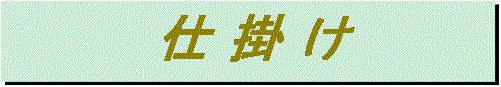
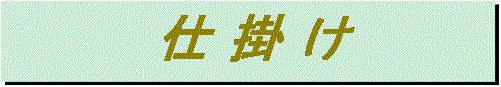
仕掛けにおいても釣る環境に合わせて選択することが肝要であるが、ここでは一般的な大きさや長さを記載した。
HomePage
へらぶな釣り
釣り具
釣り方
ご意見・ご感想
1.仕掛けの構成
①スナップ付きタル型サルカン:竿先とミチ糸を結ぶ。より戻しの効果もある。通常はサイズ12程度。
②ミチ糸:竿先からの釣り糸。通常は0.8~1号。また、長さは竿より20~25cm長い程度が適当。
③浮き:魚信を検知する。へらぶな用の浮きトップの細いものを使用。
④ゴム管:ゴム管により浮きをミチ糸に固定する。
⑤板おもり:エサ付き針を沈める。浮きとのバランスをとるように量を調節する。
⑥三つまた:より戻し付きのものがよい。針を2つ付けるための分岐具。
⑦ハリス:針に直接結ぶ釣り糸。通常0.6~0.8号。大物のへらや障害物に引っかかった場合、ハリスを切って針だけの損失にする安全装置。
10cm及び25cm程度の長短のハリスとする。
⑧針:釣り針。通常スレ5号。春・秋の暖かい時期は大きめの、寒い冬季は小さめの針を用いる。
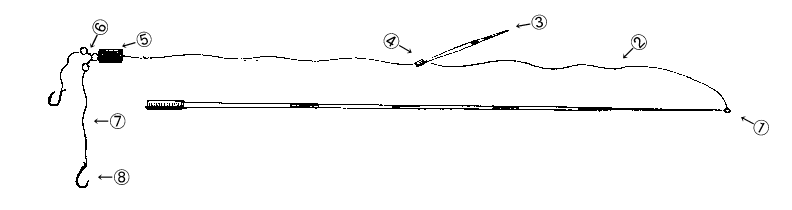
2.糸の結び方
(1)針との結ぶ方
結び方は種々あるが、中高年で老眼に優しいお薦めの結び方は下記の外掛け。
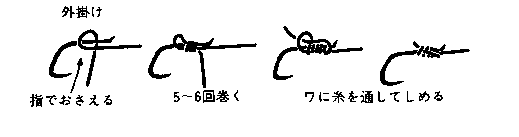
(2)サルカンや三つまたとの結び方
マルカンや三つまたへの糸のお薦めの結び方は下記のとおり。ほどける恐れのある場合は更に蝶結びにて補強する。
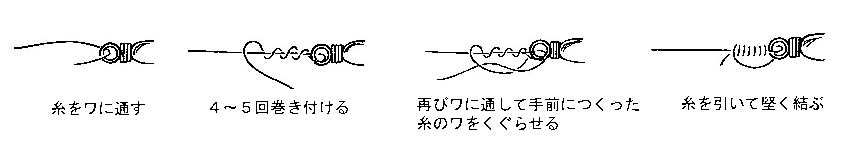
3.浮き
へらぶな釣りは針に練り餌を付けて池の中に溶解・拡散させ魚を集めるため、練り餌の針に残っている量を検知する必要がある。
その検知方法は浮きトップの沈み方で見極めるため、餌の重量が敏感に浮きに現れるよう浮きトップが細くなっているのが特徴である。
釣り場の環境により種類も多いが、最初はやや太めの浮きが扱い易いだろう。感度を高くしたい場合はトップの細い浮きに順次替えてゆくのが無難であろう。また、市販の浮きだけでなく自分にあった手作りの浮きでへらぶなと対話する喜びは釣りの魅力を倍加させる。現在は浮きの材料は全て市販されているが、市販浮きの浮きトップだけでも改良してみるのも手間の割に楽しいものとなるだろう。
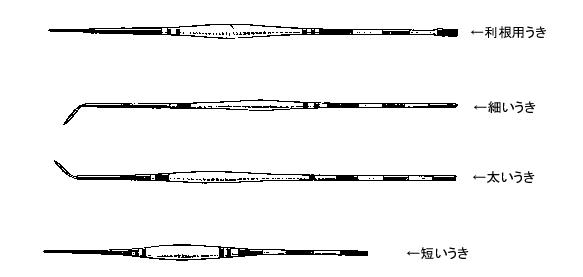
HomePage
へらぶな釣り
釣り具
釣り方
ご意見・ご感想