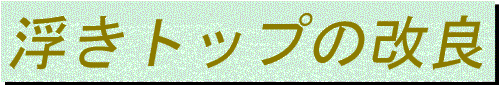
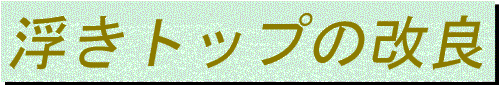
市販の浮きに少し手を加えて浮きトップを自分好みに改良するだけでも、へらぶな釣りの楽しさが倍加います。
HomePage
へらぶな釣り
釣り具
仕掛け
釣り方
ご意見・ご感想
1.浮きトップ改良の材料
(1)浮き
市販されている安価な浮き(200〜500円くらいの浮き)を用意する。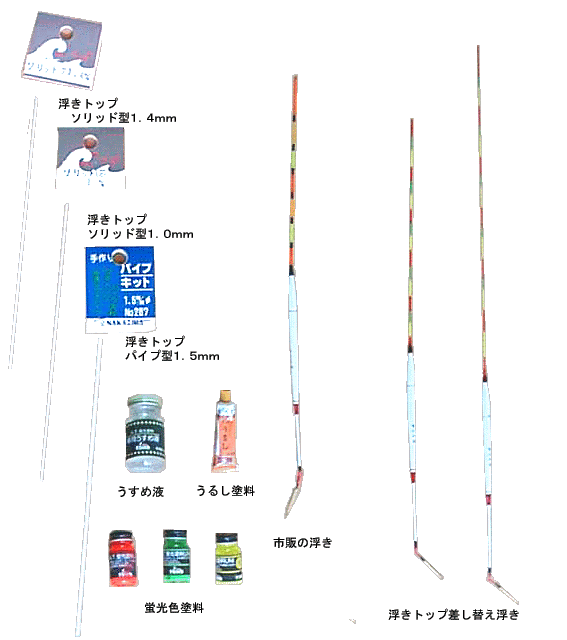
(2)浮きトップ
浮きトップはパイプ型とソリッド型の2タイプがある。パイプ型の中空構造に対し、ソリッド型は円柱構造となっている。
パイプ型は浮きトップの比重が小さいため、立ちやすい反面浮力が大きくなるので餌のついている時とついていない時の目盛り幅が小さくなる特性がある。従って、一般的にはあたりの感度が悪い傾向がある。
一方のソリッド型は中空部分がないため、比重が大きく重いことから浮きトップを大きくとり過ぎると浮きが立たない不良浮きになるリスクがある。しかし、目盛り差が大きく、少しのあたりでも大きく沈み込むため感度が良い傾向にある。なお、径は0.6〜2.0mmくらいまで0.2mm間隔で市販されている。
(3)塗料
見やすい目盛り用の塗料として蛍光色の塗料があり、赤・緑・黄色・黒などの塗料が市販されている。黒色は塗料の境界として使用されるため必ずしも必要ではない。また、よく目立つのは赤と黄色の2色で緑色は水面の色に同化しやすくやや目立たない色である。
他に防水用として、うるしの塗料を、また塗装用塗料のうすめ液も用意する。
(4)その他
塗装をするためのはけなどがあればきれいにむらなく塗装できる。
2.浮きトップの設計と製作
ここではソリッド型の浮きトップの設計例を紹介します。
(1)浮きトップの径
まず、浮きトップの径を決めてその径の浮きトップを用意する。径が大きい場合は浮きの目盛りは見やすくなるが、あたりの沈み込む幅は小さくなる。視力と相談の上、浮きトップの径を決める。通常は1.0〜1.6mm程度がよいと思われる。
(2)浮きトップの長さ
下記の計算を参考にして所定の長さに浮きトップを切断する。
○エサによる沈み込み幅の計算
いもグルテンのエサを約15mmの大きさで2ケ付けたときのソリッド径2.0mmの時の沈み込む目盛り幅は9cm。但し、塗装膜の厚さは0.1mm。それ故、πr2×L=π×{(2.0+0.2)/2}2mm径×90mm長=340mm3 という実績値から
1.4mm径の場合は π×{(1.4+0.2)/2}2mm径÷340mm3=170mm長 となる。
なお、径が細い方が浮きトップの重量が軽くなりその分重りを重くできるので、水面に立ちやすい。
○浮きトップの取り付け代 10mm
○エサを付けた時の水面上の浮きトップ長 50mm
とすると浮きトップ長さは 10+170+50=230mm となる。
(3)浮きトップの取り付け
市販の浮きトップを基から折り曲げて除去した後、浮き上部に浮きトップ径と同じ孔をドリルにて10mm程度の深さであける。
そこに接着剤にて浮きトップを浮き本体と一直線になるように取り付ける。
(4)塗装
長さに応じて、赤・緑・黄色の塗料を組み合わせて帯状に塗装する。つまようじで濃い塗料をそのまま塗ってもかまわないが、薄め液で薄めて乾かしながら何度も重ね塗りをすると色むらがなくきれいに仕上がる。なお、この際浮きトップの先端は最も見やすい赤を使用して帯の長さも長めにとるとよい。
最後に浮きトップの取り付け部に浮きに水が浸み込まないように、うるし液を塗装する。