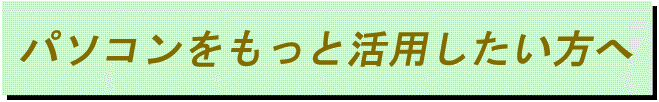
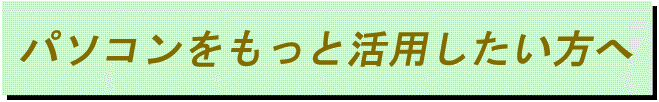
このページは多額の投資をしてパソコンを購入してメールやたまにインターネットをしているが、もっとパソコンを効果的に活用したい、または使いこなしたいと考えている方へのページです。
特に活用しなくともいままでのやり方で間に合うから
いままでのやり方の方が早いから、楽だから
操作方法がわからないから、覚えられないから、すぐ忘れてしまうから
操作方法のマニュアルが厚く、読む気になれないから
操作方法のマニュアルを読んでもすぐ眠くなるから
ソフトの組み込み方法や設定する方法がわからないから
キーボード入力に時間がかかるから
試してみたけど正常に動かなかったから
パソコンと向き合っている時間がないから
この中にひとつでも思いあたることがあれば、このまま先を読み進んでみてください。
以上のように、悪循環になっているのがわかります。それ故、どこかの循環の鎖を断ち切るとよいわけです。
断ち切りたい項目のリング内をクリックすると対策のところへジャンプします。
でもその前に大事なことがひとつあります。それはどの場合でも「パソコンに何をさせるか」を決めることです。
パソコンに向かう時間がない忙しい方には特に必要です。
コンピュータは知能をもつものも最近増えてきましたが、それでも一般に出回っているパソコンは金槌や鋸と同様に道具のひとつに過ぎません。使い方によっては今まで苦労してやっていた仕事を短時間でしかも正確にやり遂げてくれます。パソコンに仕事を肩代わりさせてわれわれを仕事の一部を解放して時間をつくってくれることも可能にしてくれる道具です。
普通は何に使うか必要に迫まれて道具を購入するのですが、パソコンの場合は組み込むソフトにより何でもできる万能選手ですから、目的がはっきりしないまま購入する場合も少なくありません。
一度に全ての使い方をマスターするのは不可能に近いことなので、もっとパソコンを活用するためには更に便利になる使い方を絞り込み、その目的のためにいろいろやっている内に自然と知識や技能が向上していき、これを何度も繰り返して活用範囲を広げていくと最終的にはパソコンを十分に使いこなしている状態になります。
まず、「パソコンに何をさせるか」を考えることから始まります。
パソコンの得意技は (1)手順がはっきりしている作業 (2)何度も繰り返す作業 (3)計算 などです。
まず第一に今「面倒くさい」と思ってやっている単純作業をパソコンにやらせることを考えてみることです。
第二に「便利になること」を考えてみることです。パソコンの得意技を考慮して、現在より便利になるようなことを想像してみるとよいでしょう。
また、市販されているソフトを参考にしてみるのもよいと思います。
第三にそれでもよい活用方法が思いつかない場合は、パソコンと仲良くなるためにとりあえずゲームで遊んで楽しむことを選んでみるのもよいでしょう。その際、ゲームも飛行機、ヘリコプター、電車、自動車の操縦シミュレーションや冒険物語のアドベンチャー・ゲームなど数多くのゲームがありますから、パソコン・ショップに出向き自分にあったゲームソフトを探すことも必要です。
○活用の例
例えば、「この文章をワープロで印刷する」、「表やグラフの入った文章をワープロでつくる」、「宛名書きを印刷させる」、「このデータの表やグラフをつくる」、「パソコンを自動的に起動させる」、「パソコンを自動的にOFFにする」、「自動的にデータをバックアップさせる」、「デジカメの画像をきれいに印刷させる」、「この文章をもとにホームページを作成する」、「家計簿として表の縦横を自動的に計算させる」などなど
○操作方法のマニュアルが厚く、読む気になれない
○操作方法のマニュアルを読んでもすぐ眠くなる
どのソフトにも分厚いものもあれば数枚のマニュアルが必ずついています。特に分厚いマニュアルは見ただけで読む意欲を減退させてしまいますが、気にすることはありません。最初から丁寧に読む必要はありません。必要なところだけを読んでいけばよいのです。でも最初はどこが必要なのかもわからずはじめのページから読むしかない場合もあります。
その時はどんなことができるか(どんな機能が使えるか)だけに絞って、読むとよいでしょう。そしてやらせたい仕事が具体的に決まったら、そのときにもう一度関係するところだけ操作方法について絞って読んでいきます。
でも、読み進んでいると10分もしない内に眠くなってくるものです。その時は読むのを止めてマニュアルとおりに動くか実際に操作してみます。操作をしてもマニユアルどおりには動かないなど疑問を感じてきたら、再びマニュアルを読むようにします。なお、マニュアル抜きで、操作をいろいろ試したい場合は「ヘルプ」メニューを参考にしてください。
また、マニュアルと操作を繰り返しをしている内に自然と必要な部分の理解できてきます。最初に読むときは「何ができるか」だけを考えて読み進むとよいでしょう。
そのできることがパソコンにさせたいと思っていることと関係がある時はマニュアルの記載してあるところを覚えておきましょう。ひととおりマニュアルを読み終えたら、その部分を再びじっくり、今度は操作方法に重点を置いて読んでいきます。その他はトラブルが生じた時とか、新しい機能を発揮させたい時に改めて読めばよいと思います。
即ち、
①必要な部分のみ、拾い読みをする
②眠くなったら、マニュアルどおりか操作してみる。
③必要最低限を理解できたら、後はトラブルの時などに改めて読んでみる。
マニユアルを読む上で大切なことは最初からすべての知識を覚えようとしないことです。
そして、実際に操作してみてマニュアルどおりになるかどうかを確かめることです。
基本的にはマニュアルを見て、操作方法を理解する必要がありますが、マニュアルなしでいきなり操作をしてもできないことはありません。その場合は、アイコンはなくともメニューにない機能はありませんので、アイコンを無視してメニューにある全ての項目をクリックして、画面がどう変わるかを見ると操作方法を理解する参考になります。また、メニューの右端には「ヘルプ」がありますが、ここをクリックしてキーワードを入力して参考にすることも効果があります。
まず、覚えようとしないことです。人間誰でも一度や二度では覚えられないのが普通です。「覚えられない」、「すぐ忘れる」というのはそれだけ数多く操作していないからです。別な言い方をするとさほど重要な操作ではないからです。気にすることはありません。ただ、忘れるかも知れないと感じた場合はどこかにメモをしておくか、マニュアルのどのページを見たら思い出すかを覚えておくことです。忘れたらその方法で思い出し、また忘れたら思い出しを繰り返すと頻繁に行う操作はその内に確実に覚えてしまいます。それでも覚えられないのは操作する頻度が少ないためですから、その都度メモなどを見て思い出してもそれほど支障はないといえます。
逆にいうと覚えるためには、それだけ多く操作して見ることが必要です。
また、ひとつの処理をする場合操作方法は複数あります。場合によっては3~5通りもある場合もあります。通常は画面上部にあるメニューと呼ばれる部分とアイコンの最低でも2方法はあります。アイコンは操作のスピードを早く効率的に入力するためににあります。またメニューは操作手順が多く操作は非能率的ですが、どのソフトにも共通しているのが特徴です。
最初の内はスピードよりも確実性を求めてメニューによる操作だけを覚えるようにして覚える量を減らしていき、操作方法も一通りマスターしてもっと早く操作したいという気持ちになったら、アイコンでの操作に切り替えのがよいでしょう。
更に、覚える内容を選別することも有用です。
最初は「何ができるか」だけを覚えます。つまりできるかできないかだけですから、比較的簡単に覚えられます。次にそれをやらせるためにはマニュアルのどこに記載されているかを覚えます。ページ数まで覚える必要はありません。大体このあたりと目次を見みながら特定できればOKです。
最後に、マニュアルの操作方法の手順を見ながら、実際にやってます。このプロセスを何度も繰り返しているといつの間にかマニュアルなしでできるようになります。
○キーボード入力に時間がかかる
キーボードによる入力は最初は次に押すキーがどこにあるかなかなか見つからず、時間がかかってしまうことはパソコン操作の上でダレでも経験することです。文字の入力は「かな」と「ローマ字」入力の2種類がありますが、キーの種類は26文字でローマ字の方が少ないため、早く覚えることができます。しかし、ローマ字入力は文字を頭の中でローマ字に変換した上、かな1文字に対しローマ字は2文字となるので、その分多くキーを叩かなければならないデメリットもあります。
どちらがよいかは各人が決めることでありますが、現在は圧倒的に「ローマ字」入力派が多いようです。
いずれにしても、キーボード入力をスムーズにするためには時間をかけて覚える他ない訳で、パソコン・ショップにはキーボード入力の練習ソフトも多く販売しているので、これらのソフトを利用して遊びながら覚えるのもよい方法と思われます。
また、パソコンはコピーとペーストという得意技があります。同じような文章や文字列を前に入力したことがあり、保存されているのなら、その部分をコピーすることにより、入力を効率的におこなうことができます。
○パソコンと向き合っている時間がない
この問題も多くの人が該当する項目と思われますが、次の2とおりの状況が考えられます。
通常は、キー配置や操作方法などがわからず、キーボード入力などパソコン操作の確認に多大の時間を要している。
のケースが多いと思われますが、現在の仕事をパソコンに肩代わりさせて、時間をつくる。即ち、始めは逆により忙しくなるが、長期的には時間をつくれるようになります。
この部分での改善(悪循環の鎖を断ち切る)は難しく、他の要因の改善を選択することで結果的に時間がとれるようになる例が多いようです。
○いままでのやり方で間に合う、早い、楽
確かに、キーボード入力などでかなりの時間を要してしまうと、いままでの方が早い結果となり、また、新しいことを覚える必要がないので「楽」という結論になるのはよくあるケースと思います。いままでのやり方でよいのであればパソコンという道具は必要としない訳です。
大工作業がなければ大工道具は不要ですから、パソコンという道具を使う仕事がなければ同様に必要はないのです。「パソコンを使って何をしようか」ではなく、「この仕事はパソコンにできないか」と考えた方がよりよい活用ができるのではないかと思います。
いずれにしても、パソコンにやらせることが明確になればこの問題もクリアしていくものと思います。
○正常にソフトが動かない、ソフトの組み込み方法や設定する方法がわからない
まず、「ハードの環境(パソコンの性能やハードディスクの空容量、基本ソフトなど)がソフトの要求を満たしているか」を確認してみてください。
ソフトのケースやマニュアルにソフトの要求仕様が記載されています。一方パソコンのシステム情報にてパソコン側のデータを確認することができます。それら2つの情報を比較して要求仕様が満たされているかを確認します。
また、うまくいかない時は最初に戻ってひとつひとつ確認しながらステップを踏んで操作することが大切です。要求仕様が満たされていたらまず動作しないということはありません。どこかでマニュアルに記載されていることを見逃したり、早とちりをしてマニュアルとは別の操作のためトラブルになっているのでほとんどです。
パソコンは「パソコン」と「パンコン」では区別します。人はどちらも「パソコン」と認識してうまく修正してくれますが、パソコンは最後の「ン」とサシスセソの「ソ」の字は別の文字として修正をしてくれません。融通のきかない頭の固い機械だと認識する必要があります。
それ故、マニュアルのとおりに一字一句正確に操作してみてください。
以上を確かめた後、今一度マニュアルを読み返してチェックしてみてください。それでも駄目な時はソフトの技術サポートの助けが必要ですが、インターネットのソフト会社のホームページの技術サポートのページにある「よくある質問(FQA)」を閲覧すると往々にして同じ問題が掲載されている場合がありますので、そちらも確かめてみてください。
なお、組み込み方法・設定方法についてより詳細な対処法は「トラブル対応」のコーナーを参照ください。
○利用したいアプリケーション・ソフトが高価
欲しいアプリケーション・ソフトが高価で手が出ずということも多いと思いますが、ここでは無料または安価で入手できる方法を紹介します。但し、ボランティアで提供しているものが多いため、技術的なサポートはまず期待できないので、最初は多少負担はかかっても一般に市販されている方をお薦めします。
一般にアプリケーション・ソフトにフリーウェアと記されている場合は無料、シェアウェアの場合は寸志程度の金額という意味です。
下記のインターネットのページにはいろいろな種類のソフトが紹介されていますから、探して見るのも面白いと思います。
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/
○パソコンを壊すかもしれない
○何も応答しなくなった
マウスは勿論、キーボードを叩いてもウンともスンとも言わなくなることはよくあることです。その時にまず問題のプロクラムを終了させたり再起動を試みましょう。それらの操作方法はこちら。
パソコンの場合、ハードが物理的に故障することは極めて希で、私もパソコンを購入して7~8台で約20年くらいになりますが、フロッピー・ディスクを例にとっても今まで一度も故障したことがありません。キーボードや本体においても同じです。
どんなに激しく使用しても通常の使い方をしている限りはそんなに故障することはありません。もし万が一、故障した場合は使用の仕方が悪いのでなくパソコンの方が悪いのだと思った方がよいではないかと思っています。
○画面の中の画像が小さく、ダブル・クリックが不得手
ダブル・クリックは二度続けて早くクリックしないとうまく動作することはできません。その場合はダブル・クリックの時間間隔を長くするように設定することができます。「スタートボタン」→「設定」→「コントロールパネル」→「マウス」の「ポタン」タブにて「ダブルクリックの速度」で設定できます。
ダブル・クリックが苦手な方はこの方法の方は、画像にポインタを置き、右クリックすると小さなウィンドウが開きます(右図) 最上部の「開く」をクリックするとソフトが起動します。この方法は時間を要しますが確実に操作できます。
ダブル・クリックする画像が小さくてダブル・クリックがしにくい場合があります。その場合は下記の「画像が小さい」をご覧ください。
○パソコンを起動して使用するソフトを起動するまでの操作が面倒だ
パソコンの電源を入れていつも使用しているソフトを自動的に起動させるように設定することが可能です。いつも同じソフトを起動させる場合に便利です。
「スタートボタン」→「設定」→「タスクバーと「スタート」メニュー」にて「「スタート」メニューの設定」タブで「追加」ボタンをクリックして、コマンドラインの欄に起動させるプログラム名を記入する。なお、記入する内容は起動したいアイコンを選択して右クリックしたメニュー(上右図参照)の最下段の「プロパテイ」をクリックした時に表示されるリンク先をそのまま入力する。但し「”」は除く。
○画像が小さい
画面の解像度を設定して画像を大きくすることも可能です。但し、画面が大きい場合は全てが表示できないため、画面を左右・上下に動かさなければならない不便さを伴うことがありますので、操作の煩雑を考慮の上適当な画面の大きさを設定してください。
設定は「スタートボタン」→「設定」→「コントロールパネル」→「画面」の「設定」タブにて「画面の領域」で「小」の方にスライドさせて「OK」ボタンをクリックすると画面全体が大きくなります。逆に画面を小さくして広い範囲を表示させるには「大」の方に設定します。
○文字が小さい
「画像が小さい」と同様に画面の解像度を低くする(小に設定)と画像と共に文字も大きくなります。また、使用するソフトにより文字を大きくすることができます。例えば、一太郎9では「表示」→「画面表示設定」の「ドラフト編集」タブや花子9では「表示」→「表示倍率」で設定可能です。ワード2000、エクセル2000やパワーポイントでは「表示」→「ズーム」で大きな表示にすることができます。また、インターネット・エクスプローラでは「表示」→「文字のサイズ」で、ネットスケープ・ナビゲータでは「表示」→「フォントを大きくする」にて設定できます。
更に、印刷プレビューができるソフトの中には印刷プレビュー画面にある画面の大きさを変更する機能にて文字や画像を大きくすることもできます。